
応答速度はゲーミングモニターにとってとても重要な値です。ですが、理解するには液晶ディスプレイに関するやや専門的な知識が必要なので、はっきりと意味がわからないままにしてしまっていないでしょうか?その結果、せっかくのハイパフォーマンスモニターが低価格で販売されていても逃してしまったり、高性能と思っても期待通りの画質が得られなかった、ということになっていないでしょうか?本記事では、そうした悩みを解消するため、初心者や一般ユーザー向けに応答速度の基礎知識から丁寧に解説します。その後、ゲーミングモニターとしてどのような点が重要なのか、1ms・2ms・4ms・5ms・8ms・10ms・14msで何が違うのか、実際に購入にあたって、どのような基準で選択すれば快適か解説します。本記事を読んで頂くと、自分にとって適切なゲーミングモニターを確実に選択できるようになります。
モニター・ディスプレイの「応答速度」とは
モニターやディスプレイの応答速度とは、液晶画素が光の透過状態を切り替える反応の速さを意味しています。以下で具体的に解説します。
応答速度の意味
応答速度の意味を解説していきます。
黒→白→黒に変化する時間
黒→白→黒、と画面が変化する時にかかる所要時間を応答速度とするのが、最も一般的に使用される応答速度です。
液晶ディスプレイ・モニターの性能
液晶ディスプレイやモニターの性能を表す重要な指標が、応答速度です。応答速度は、画面の切り替わる速度なので短ければ短いほど、画素の色が素早く変わるということなので、性能が良いということを表しています。(高いほどよいは誤解です)
応答速度はモニターやディスプレイの詳細表記に記載されています。
単位はms(ミリセカンド)
応答速度の単位はms(ミリセカンド)です。できるだけ小さい値とより高性能です。多い、少ないと表現することもあります。時間の長さを意味しており「秒」に換算できます。
〇msを秒に換算すると以下のようになります。
| 〇msは何秒? | |
| 8ms | 0.008秒 |
| 2ms | 0.002秒 |
| 5ms | 0.005秒 |
| 0.1ms | 0.0001秒 |
| 1000msec | 1秒 |
msの読み方
msの読み方はミリ秒(びょう)、ミリセカンド、ミリセックのいった読み方があります。
〇msを秒に換算すると以下のようになります。
応答速度とリフレッシュレート(hz)の違い
応答速度とリフレッシュレート(hz)は違うものですが、関係が深いです。その違いを説明します。応答速度は、液晶画素自体の性能です。印可電圧に対して分子配列を変更する動きの、反応の良さを表しています。それに対して、リフレッシュレートは、ディスプレイ制御回路の性能です。「ディスプレイ制御回路が、液晶面全体の電圧を制御する回数=全画素の色を変更する回数」です。つまり、リフレッシュレートに対して、応答速度が追従できるかどうか、という関係になっています。
言い換えれば、応答速度がリフレッシュレートを上回らないと性能を発揮できません。
リフレッシュレートは以下の記事でも解説しています。

参考として、応答速度とリフレッシュレートごとの対応関係を以下に示します。
・計算式
「1000ms÷応答速度=追従可能なリフレッシュレート」
・再掲:応答速度と追従可能なリフレッシュレートの最大値
・1ms → 1000hz
・5ms → 200hz
・10ms → 100hz
・16.7ms → 60hz(最低限の基準値)
モニターのhzとは
モニターのHzは、リフレッシュレートを指しています。モニターが画面を1秒間に更新する回数です。
パネルの種類と応答速度
パネルの種類と応答速度の特性について、以下に代表的な3種類を紹介します。このほかにもさまざまな発展型の液晶が存在します。
・VA系
垂直配列(Vertical Alignment)なのでVA系といいます。無電圧では分子が垂直に整列しており、電圧を加えると、水平になります。応答速度は3種類の中で最も良好です。応答速度の目安は、1ms~2msです。
・TN系
ねじれネマチック液晶(TwistedNematicLiquidCrystal)なので、TN系と言います。無電圧では、液晶分子がねじれた状態で並んでいます。わかりにくいですが、これは光もねじれて変更板を通過できる向きに変わるので、光を通します。電圧を加えると、分子が回転してねじれが解消され、光が変更板に遮られます。応答速度は3種類の中で、中間です。応答速度の目安は3ms~4msです。
・IPS系
イン・プレイン・スイッチング液晶(In-Plane Switching)なので、IPS系と言います。無電圧では分子がモニタ面に対して平行に並んでいます。電圧をかけても、同じ面内(イン・プレイン)で水平回転することで光の透過性を変更します。応答速度は3種類の中では最も遅いです。応答速度の目安は5ms~8msです。
液晶モニターの応答速度と残像の関係
液晶モニターの応答速度と残像の関係について説明します。
液晶モニターの残像
液晶モニターの残像は、描画色を変更する速度が遅い事で、切り替え前の色が残って見えてしまうことにより発生します。リフレッシュレートの1回の画面更新よりも応答速度が長いと、画素の色が変化しきらず、残像になります。
GtoG(Gray to Gray)とは
GtoG(Gray to Gray グレートゥーグレー、gtgとも表記)とは、無彩色の中間色から中間色への切り替え速度を表しています。これは、黒→白→黒、とする場合の対照といえます。液晶画面の画素の明るさは、電圧によってコントロールされていて、RGB3色に対応する電圧を別々にかけています。黒→白→黒、に切り替える場合は電圧が最大と最小なので、切り替わりが早いのですが、GtoGの場合は、より弱い中間の電圧によって制御するため、応答速度が遅くなります。
【テレビ/ゲーム】応答速度の目安は?
応答速度の目安を考えるとき、リフレッシュレートと比較して決める点に注意しましょう。リフレッシュレートはモニターが画面を更新する速度です。ですから、リフレッシュレートよりも高速に画素の色を変更できる=応答速度が速いことが求められます。リフレッシュレートを上回る性能の応答速度のモニターを購入するとして、ゲームやテレビで求められる応答速度の目安はどのくらいでしょうか?
テレビ・液晶テレビ
一般的な液晶テレビの応答速度は10ms前後です。日本放送が30fpsなので、普通にテレビを視聴したいのであれば10msの応答速度があれば問題ありません。
fpsは以下の記事でも解説しています。

テレビを、ゲームプレイに使っている場合は遅い場合があります。REGZAといったハイセンステレビでは0.83msを実現しておりゲーミングディスプレイを超えるものも存在しているので、遅いと感じたらテレビのmsを確認しましょう。
ゲーム
ゲームプレイに求められる応答速度は、映像を出力するゲーム側の仕様によりますが、5msを目安にしている人が多いようです。一般的なゲームであれば5ms、FPSや格闘ゲームでは1msの応答速度のモニターがおすすめとされています。
「1ms」と「5ms」の違いは?【2ms・4ms・8ms・10ms・14msの体感】
ゲーマーに推奨される応答速度1msと5msはどれくらい違うのか、わかりやすい形で比較してみましょう。まずは、先述の応答速度とリフレッシュレートの関係を再掲してから、話を続けます。矢印の左が応答速度、右が追従する限界のリフレッシュレートです。快適なのはどちらでしょうか。
<応答速度と追従可能なリフレッシュレートの最大値>
・1ms → 1000hz
・5ms → 200hz
・10ms → 100hz
・16.7ms → 60hz(最低限の基準値)
最低限のモニターのリフレッシュレートが60fpsであることを考えると、1ms・5msがいかに高速かわかります。応答速度が短いモニターほど、フレームとフレームの間の物体の移動状況をより細かく視認できるようになります。この差は、数画素程度の画像(遠方の敵)を認識して状況判断しなければいけないような、シビアな環境で戦う FPSゲームで特に顕著で、成績に影響を与えます。
応答速度1msと5msの違いは?
応答速度1msと5msはどれくらい違うのでしょうか。実際、1msと5msは見た目では違いがわからないと感じる人が多いようです。どちらも一般的なゲームプレイには十分とされる応答速度です。ただし、一瞬のラグが勝敗を分けるようなゲームをプレイするなら1msを選んでおいた方が気休めにはなるかもしれません。
応答速度1msと2msの違い
応答速度1msと2msの違いは実際体感できないほどです。どちらも十分速いです。0.001秒の差が体感できるなら1msの方を購入してもよいかもしれません。
応答速度4ms・5msは遅い?十分?
応答速度4ms、5msはテレビや一般的なゲームをプレイするのに十分な応答速度です。
遅いということはありませんが、ガチ勢であれば上のものを購入してもよいかもしれません。
応答速度8msはゲームに遅い?
応答速度8msだと、リフレッシュレートは125Hzまで追従できます。1世代前の映像信号伝送規格「DVI」の最高周波数144Hzまでは追従できず、HDMI規格でも中程度の水準です。ゲーム用としては標準的なスペックになり、安価な製品が市販されているので、60Hz製品から乗り換えると、体感的にはかなり改善されて感じられます。8msがゲーム用のモニターで遅いかどうかは、ゲームの解像度設定と見比べる必要がありますが一般的にはやや遅いかもしれません。
ガチ勢でなければ6msあれば通常プレイには問題ないと感じる人が多いようです。
応答速度10msは遅い?
応答速度10msはテレビの視聴には問題ありませんが、ゲームプレイにはやや遅いと感じる人も多いです。
応答速度14ms
応答速度14msでは、リフレッシュレートは71Hzまで追従できます。これは製品の性能としては、最低限の水準である60Hzをサポートするものになります。この速度は、動画が滑らかに見えるためのギリギリの速度です。従って、非常に低価格な製品を見つけることができます。誰でもこの性能は持っているので、ゲームの競争力が高まることはありません。
応答速度の測定・確認方法
自分のモニター・ディスプレイの応答速度がわからない場合はどうすればよいでしょうか。
応答速度の測定方法は、以下があります。
1.製品の説明書をみる
液晶モニター・テレビ・ディスプレイの説明書に記載されている数値を確認します。メーカーが発表している製品の仕様が記載されています。
2.測定サイトで体感を調べる
ただし説明書の数値はあてにならない場合が多いです。体感を調べたい場合は、計測サイトを使用して調べる方法があります。UFOテストというサイトでは画面に流れるUFOの映像と残像の発生からあなたのテレビやモニターの体感の応答速度がどれくらいか測定できます。
https://www.testufo.com/ghosting
PCやスマホのモニター応答速度の測定に対応しているスピードテストサイトで行います。
自分のモニターやディスプレイのmsが知りたいときは対応しているサイトで測定してみてください。
具体的なサイトは、msの単位を使うpingの計測方法として以下の記事で解説しています。
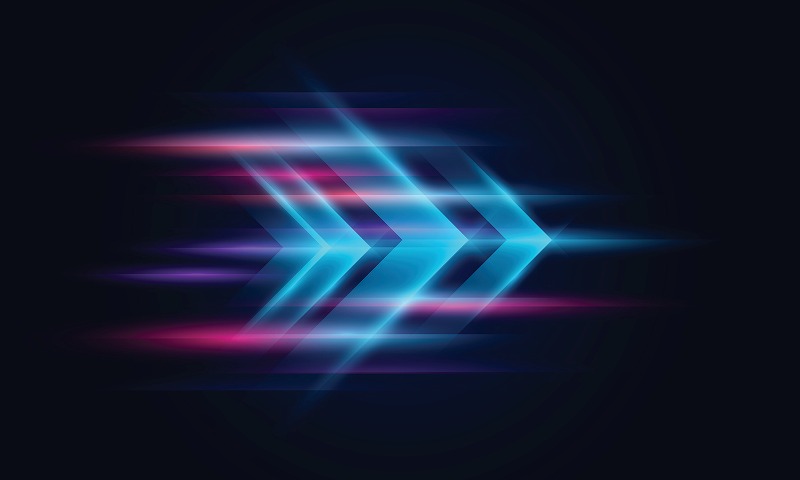
応答速度はゲーミングモニターに重要
応答速度は、ゲーミングモニターにとって重要です。
以下で解説します。
ゲームに快適な応答速度の目安?
応答速度が重要なゲームを挙げます。プレイに直接影響があるのは、リアルタイムに状況判断する必要があるタイプのゲームです。
2Dシューティングゲーム
2Dシューティングゲームでは、多数の弾幕を避ける必要がありますので、残像が無く、応答速度が早いことが重要です。推奨の応答速度は、10msです。
FPS・TPS
FPS・TPSは、精密な照準を0.1秒でも早く敵に命中させることが勝敗に直結します。また、遠くの小さな敵を正確に狙い撃つことも必要です。そのため、画面切り替えが高速で、残像の無いモニターを必要とします。推奨の応答速度は、5msです。
格闘ゲーム
格闘ゲームは、正確な操作と反射神経が要求されます。その能力がしっかり反映されるモニターが必要です。応答速度が遅いということは、誤認しやすく、反応も遅れることになってしまいます。推奨の応答即では、5msです。
リアルタイムアクションRPG
リアルタイムに行動するアクション性の高いRPGゲームは、上述のタイプと同様の要素を持っているため、応答速度が高いモニターを必要とします。推奨の応答速度は、14msです。
応答速度が速いメリット
応答速度が速いメリットは、画面発色の精度が良く、高速なリフレッシュレートに追従できることによって生まれます。それはすなわち、ゲーム中のオブジェクトを、より現実世界に近い精度で認識できるということです。その結果、多数の競争相手と比較したとき、より早く的確な行動を取りやすくなるので、勝率が上がります。
モニター応答速度はオーバードライブで速くなる?
モニター応答速度は、オーバードライブで早くなります。どのような仕組みでそうなるのか、まずは、オーバードライブとは何か、という基本的なことから確認していきましょう。
オーバードライブとは
オーバードライブとは、画素の明るさを制御する電圧を、通常より高い電圧でかけることで、急激に応答させ、立ち上がり速度・立下り速度を高速化するというものです。
オーバードライブのデメリットはない?
オーバードライブにもデメリットはあります。高速化のために電圧を高くするため、立ち上がり電圧が色調に適した目標電圧を、短時間の間わずかに超える「オーバーシュート」と、逆にそれとは対称的な形で、立下り電圧が目標電圧を下回る「アンダーシュート」が発生します。ちょうど、加速した自動車が急ブレーキを踏んでも、慣性力によって止まり切れないのと同じ状態です。電圧が変動するということは、画素の色調が不安定になるので、残像が発生することがあります。
ゲーミングモニター選びの基準
ゲーミングモニター選びの基準について解説します。
ディスプレイケーブルと解像度を確認
ディスプレイケーブルとプレイしたい解像度を確認することが最初に必要です。
以下のリストが、普及しているディスプレイケーブルと、対応リフレッシュレート(ここでは読みやすさのため、Rとする)の関係です。
ディスプレイケーブル・解像度・リフレッシュレートの関係
・DVI ・・・ 解像度:2560×1600 → R:60Hz
・DVI ・・・ 解像度:1920×1080 → R:144Hz
・HDMI1.4 ・・・ 解像度:3840×2160 → R:60Hz
・HDMI1.4 ・・・ 解像度:1920×1080 → R:120Hz
・HDMI21.4 ・・・ 解像度:3840×2160 → R:144Hz
・HDMI2.1 ・・・ 解像度:1920×1080 → R:240Hz
・最低限の速度 ・・・ 60Hz
上記のリストに示したように、モニターが実際に動作できるリフレッシュレートは、解像度とディスプレイケーブルの信号伝送速度によって制限を受けます。解像度が大きくなると、伝送するデータ量・更新しなければならない画素量がともに増加するため、描画が間に合わないリフレッシュレートでは動作できなくなるからです。
応答速度
応答速度は、リフレッシュレートから逆算します。例えば、60Hzの場合、約16.7ms以下の応答速度の製品でなければ、画面更新が間に合わず、残像が出ます。また、GtoG(Gray-to-Gray)の性能を表示している製品と、表示していない製品がありますが、表示している製品を優先して検討しましょう。表示していない場合の応答速度は、「黒→白→黒」の場合の応答速度です。これはGtoGよりも高い電圧をかけやすいので、応答速度が速くなりやすいという特徴があります。ですが、実際のゲーム画面は中間色が支配的なので、GtoGの応答速度の方が実際の表示性能に近いのです。
視野角
視野角は、あまり重要ではありません。ゲームをプレイする場合には、モニターの真正面に座っているため、視点の位置がほとんど変わらないからです。
オーバードライブ
オーバードライブ機能があるモニター(オーバードライブモニター、オーバーシュートモニター)では、これをONにすれば応答速度が改善されることがあります。詳しい内容は先述したとおりです。ですが、オーバードライブがあっても改善されない場合もあるので、できるだけ実際に改善されたという実体験の情報があるか、確認するのが望ましいです。
FreeSynch・G-Synch
FreeSynch・G-Synchは、どちらも映像データのフレームレートに、モニターのリフレッシュタイミングを同期させる技術です。G-SynchはNVIDIA製のグラフィックボードも必要です。FreeSynchはもっと汎用的で、メーカーに依存しません。これらの技術は、簡単に説明すると、フレームが完成したタイミングに合わせて描画する、ということです。どちらも、より自然で美しい映像を楽しむことができます。
おすすめゲーミングモニター
おすすめゲーミングモニターを紹介します。
Dell S2721Q
URL:製品ホームページ
GtoG応答時間が4msで、ハイスペックとコストパフォーマンスを備えたモニターです。FreeSynch技術にも対応しており、ゲーミングモニターの代表ともいえる仕様です。端子はHDMIx2、DisplyaPortx1で、2つの異なる映像を、同時に画面表示できます。4K映像も60pで鑑賞できます。
Acer VG272Xbmiipx
URL:製品ホームぺージ
GtoGでオーバードライブ時、なんと0.1msという応答速度です。通常モードでも応答速度5msなので充分高速です。リフレッシュレートは240Hzに対応しています。注意点は、G-Synchを有効にする場合は、グラフィックボードもNVIDIA製のG-Sync対応製品が必要という点です。
HP 24fw
URL:製品ホームページ
GtoG応答時間が5msと高速です。それ以外のスペックは標準的ですが、モニターとしてはかなり安価なので、すぐに導入できる点が魅力です。
wqhdと呼ばれるフルHDより高解像度なモニターも自作pcをつくるような人にはおすすめです。
また、ゲーミングモニターような応答速度が大きいモニターの性能を発揮するには、周辺デバイスがモニターの性能に追いついていることが必須になります。ゲーミングpc、ゲーミングヘッドセット、ゲーミングマウスのように対応する数値が合っているものを選ぶのがよいでしょう。同じシリーズで買いそろえると確実です。
まとめ
応答速度は、リフレッシュレートや解像度と比較して、どのような性能なのかイメージしにくいです。ですから、やや技術的な内容も踏まえて少し詳しく解説しました。応答速度は液晶自体の分子配列によって、それぞれの方式の特性が生まれているので、これを知らないことには理解しにくいままになってしまいます。ですが、一度名前の意味がわかり、構造のイメージを覚えれば、難しいことはなくなります。本記事を参考に、自分の用途と好みに最適な液晶ディスプレイを購入して頂ければ幸いです。